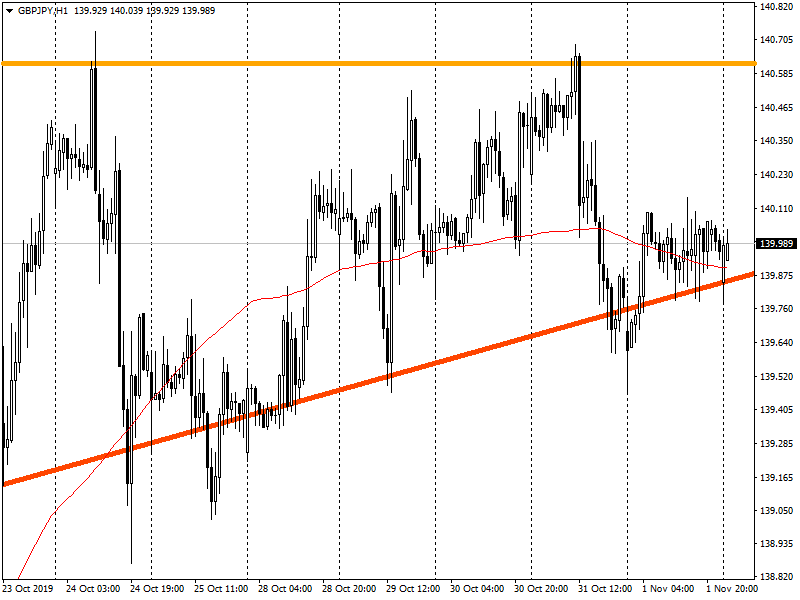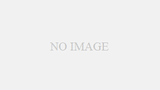MACDは「Moving Average Convergence/Divergence Trading Method」の略で、直訳すると「移動平均・収束拡散トレード法」です。
MACDは以下の計算式で算出されます。
MACD=短期EMA-長期EMA
シグナル=MACDの単純移動平均(SMA)
要するに、移動平均線の差を表しています。
MACDに用いられる移動平均は「単純移動平均(SMA)」ではなくて「指数平滑移動平均(EMA)」です。しかし、インジケーターによってはSMAを選ぶこともできます。
MACD本来の意図からはズレるかもしれませんが、単に移動平均線(SMA)の差を知りたいのであれば、SMAで計算してもいいでしょう。
移動平均線の差
移動平均線の差が広がるときは、その方向きの方向に勢いがあるため、レートが移動平均線まで戻ってきても反発する可能性が高いです。
逆に差が縮まってきている時には、既に勢いがなくなってきていますから、反転したまま移動平均線を越えて行く可能性が高まります。
というような見方ができるのですが、それを分かりやすく表示したのがMACDではないかと、私は考えています。
なので、MACDをわざわざ表示させなくても、移動平均線と移動平均線の間隔でMACDで分かることは判断できてしまいます。
MACDのパラメーター
MACDのパラメーターとしては短期EMA、長期EMAの期間とシグナルと期間を指定する必要があります
一般的には、短期EMA期間は9、長期EMA期間は26、シグナルは9に設定されることが多いです。
MACDを一般的なMACDとして利用するのであれば、この一般的な設定にしておくのが望ましいです。
ただし、MACDはもともと日足で利用することで開発されていますので、短期EMAは9日、長期EMAは26日というように単位が日になっていますので、1時間足や5分足だと若干ニュアンスが変わってくるのかもしれませんので、その辺は好きに設定すればいいでしょう。
それから、上述した移動平均線の差を視覚化するために使用するのなら、自分が使っているMAに合わせて設定した方が、チャートとのズレがなくなって分かりやすいでしょう。
この場合はシグナルに関しては表示させなくてもいいでしょうし、適当に設定してもいいでしょう。
MACDのヒストグラム
ところで、MACDにはヒストグラムもあります。ヒストグラムの計算式は以下のとおりです。
ヒストグラム=MACD-シグナル
MACDの使い方
MACD線とシグナル線の交差
MACDとシグナルがゴールデンクロス、デッドクロスかで判断されることが多いです。
ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売る・・・それだけですww
ダイバージェンス
ダイバージェンスが発生しているか否かでも利用されることが多いです。
私もダイバージェンスは確認します。
ダイバージェンスが発生しているとはどういう状況でしょうか。
下落相場の時に、レートは下がっているのに、移動平均線の差は縮まっているという状況です。
これは、長期MAが短期MAに近づいてきていることを意味します。すなわち、MAがゴールデンクロスする可能性が高まりつつあると言うことです。
MAのゴールデンクロスといれば、基本的には上昇相場に転換すると考えられるわけです。
すなわち、ダイバージェンスが発生していると言うことは、そろそろ反転するかもしれないということを示唆しています。
このダイバージェンスを見る場合は、MAの期間をある程度狭くしておかないとなかなか発生しません。
MAの期間が長い場合、MACDの山や谷ができにくいので、ダイバージェンスは確認できないのです。
逆に期間を短くすると、山や谷ができすぎてよく分からない状況になりかねません。
このあたりは、自分のルールに合わせて調整が必要です。